外苑ソーシャルアカデミーのインキュベーションフェローを務める中村仁です。
2023年7月1日、山田氏と共に設立したこの外苑ソーシャルアカデミーにおいて、私は社会と経済の複雑な構造について真摯に向き合う機会を得ました。思索の道は一筋縄ではいかず、考えがあっちに行ったりこっちに行ったりと迷走した時期もあります。その間、私たちの取り組みも、時として方向性が定まらず、チグハグに見えたことは否めません。
けれども、GSAの運営に関わりながら約1年半を過ごしてきた今、ようやく自分なりの考えがまとまってきたように感じています。これまでの経験を経て、私はこのタイミングで私の思いを整理し、言葉にするべきだと強く感じました。
多少堅苦しい表現になってしまったかもしれませんが、私が言いたいこと、伝えたいことはおそらく十分に表現できたかと思います。どうかその点をご容赦いただき、この文章をお読みいただければ幸いです。
良い社会
社会にはさまざまな人がいる。頭の切れる人もいれば、そうでない人もいる。稼ぐ才能に恵まれた人もいれば、なかなかうまくいかない人もいる。努力の結果として「強い人」になった者が成功し、幸せを手にすること自体は素晴らしい。しかし、その一方で、「弱い人」が一方的に敗北を強いられる社会は決して健全とは言えない。
そもそも、強い人が強くなれたのは、本人の努力だけによるものではない。生まれ持った遺伝的な要素、育った環境、運の積み重ね、それらが大きく影響しているのは明らかだ。同じように、弱い人がそうなったのも、単なる本人の選択の結果ではない。ならば、社会はどうあるべきか。
勝者が称賛される社会はいい。しかし、敗者が見捨てられる社会は、あまりにも冷たい。すべての人が、自分の力を最大限に発揮しながらも、弱い立場の人が一方的に敗北しない仕組み、そうした社会を築くことこそが、私たちの責務ではないかと思う。
ノブレスオブリージュ
私は決して驕るつもりはない。しかし振り返ってみれば、考える力に恵まれ、それなりに稼ぐ術を身につけ、物事を楽観的に捉えられる性格に生まれたことは、確かに私の人生を有利に運んできた。そして、それらは決して私一人の努力だけで手に入れたものではない。
知性や才能、経済的な力、精神の強さ——そうしたものは、自ら鍛え上げる部分もあるが、その土台には生まれ持った遺伝、育った環境、そして数えきれないほどの偶然が絡んでいる。両親の存在、教育を受ける機会、出会った人々、時代の流れ。そうした無数の要因が重なり合い、私は「恵まれた側」に立つことができたに過ぎない。
ならば、それを単なる幸運として享受するだけでよいのか。私が得たものは、私一人の力だけで築いたものではないのだから、その恩恵を次の誰かへと手渡していく責任があるのではないか。人は皆、それぞれの立場で誰かに支えられながら生きている。ならば、今度は私が支える番だ。与えられた力を、ほんの少しでも社会へと還元できるのなら、それこそが私に課せられた務めなのだろう。
学問のすすめ
「学ばざる者は幸せになれない」——福沢諭吉はそう説いた。その言葉に、私は深く共感する。
勉強とは、単なる試験のための暗記ではない。自然の法則を理解し、宇宙の果てに思いを馳せ、人間の営みを振り返り、未来を構想すること。それは知的な冒険であり、探究の過程そのものが喜びに満ちている。そして、それだけではない。学ぶことで世界をより深く理解し、人生の選択肢を広げ、自らの幸福を掴み取る確率を高めることができる。言葉に説得力が増し、他者との対話も豊かになる。
もちろん、学ぶことが苦手な人もいれば、勉強に苦痛を感じる人もいる。だが、それは方法や環境の問題かもしれない。人にはそれぞれ、自分に合った学び方があるはずだ。大切なのは、無理なく自分に合ったペースで知識を吸収していくこと。
しかし、学びの質は出会う知識によって大きく左右される。歪んだ情報や偏った価値観に触れてしまえば、学ぶこと自体が誤った方向へ進んでしまう危険がある。だからこそ、良質な教材に触れること、信頼できる教師を持つことが決定的に重要なのだ。健全な精神を養い、正しく学ぶ——それこそが、幸せへと続く確かな道ではないだろうか。
希望のもてない社会
日本は、先進国の中で唯一、30年以上にわたって経済の低迷から抜け出せずにいる。この長い停滞の中で、若者の約4割が未来に希望を見出せず、6人に1人が貧困の中に取り残されてしまった。かつて世界第2位の経済大国として繁栄を誇った日本は、中国に追い抜かれ、3位へと転落。そして近年、為替の影響も相まってドイツにもその座を明け渡し、ついに4位にまで後退してしまった。
GDP(国内総生産)は、単に「生産の総和」と理解されがちだ。しかし、経済学の「三面等価の原則」によれば、それは「需要の総量」であり、同時に「所得の総和」でもある。つまり、GDPの停滞とは、単なる統計上の問題ではない。日本全体として需要が縮小し、国民の所得が減少し、経済の血流そのものが滞っていることを示している。長期にわたる経済の低迷は、一過性の不況ではなく、明らかに構造的な問題を孕んでいる。
では、なぜ日本はここまで衰退してしまったのか。マクロ経済学の視点から見れば、経済の主体は「家計」「企業」「政府」の3つに分類される。今の日本において、家計は消費を控え、企業は成長への投資をためらっている。そうであるならば、残る要因は政府の経済運営にほかならない。果たして、日本の政府は、この国の未来を見据えた経済政策を実行できているのか。かつての繁栄を取り戻すために、いま何を変えなければならないのか。私たちは、この問いを先送りにすることなく、今こそ真正面から向き合わなければならない。
悪政
現代の日本の政治は、官僚主導で進められていると言われる。東大をはじめとする名門大学を卒業した優秀な人材が各省庁に入り、それぞれの分野の専門家として政策を担う。一方、政治家はどうか。彼らの経歴はさまざまであり、ある特定の行政機能に関する知識では官僚には到底及ばない。そのため、政治家は官僚の助言を受けながら政治を進めていく。これ自体は、必ずしも悪いことではない。
しかし、官僚もまた人間である。彼らにも家族があり、仲間がいる。そうした身近な人々の幸福のために、あるいは自らの地位を高めるために、時として本来の行政の役割を超えて権力を拡大しようとする。問題は、それが度を超し、国家運営の本質を歪めるほどに肥大化してしまったことだ。
官僚機構は、本来、国民のために機能すべきものだ。しかし、いつの間にか自己増殖し、国家を支配する存在へと変貌してしまった。
根本解決
国家の中枢を担う官僚たちは、まさに選ばれし超エリートである。彼らは圧倒的な知性を持ち、驚異的な集中力と勤勉さを兼ね備えている。凡人には到底真似のできないほどの頭脳と労働量で、国家運営に携わっている。その多くは、灘、開成、慶應、早稲田、東大、京大といった名門校を卒業している。だが、そうした学び舎で、本当に健全な価値観が養われているのだろうか。
私は以前、「学問とは、健全な精神を養い、正しく学ぶことが重要だ」と述べた。しかし、実際にはどうだろう。彼らは受験戦争のただ中に身を置き、幼い頃から知識の詰め込みと計算能力の鍛錬に明け暮れてきたのではないか。果たして、その過程で「持てる者の責任」を教えられたことがあっただろうか。もしそうでないなら、彼らがエリートとして社会のトップに立ったとき、国家の運営が歪んでしまうのも無理はない。
この問題に対し、竹田恒泰氏は直接的に批判したわけではないが、一つの試みを行っている。彼はエリート中学校向けの歴史教科書を制作し、将来の指導者となる若者たちに正しい国家観を教えようとしている。それは、日本の未来を考えた上での行動なのだろう。持てる者にこそ、相応の責任がある。その自覚を育む教育こそが、国をより良い方向へ導く鍵なのだと思う。
劇薬
私は先に、エリートの道徳教育が日本を立て直すための根本的な解決策であると述べた。しかし、それを実現するためには、まずエリートを育成する教員、そしてその教員を養成する制度そのものを改革しなければならず、その過程には膨大な時間と労力がかかる。では、もっと迅速に現状を打破する方法はないのだろうか。
その一つとして、暴力的な手段が浮かぶ。悪政を暴力によって挫き、政治体制を劇的に変えるというアプローチである。歴史を振り返ると、五・一五事件、二・二六事件、八・一五事件、安保闘争、浅間山荘事件など、数々のクーデターや暴動が発生し、政治体制に変動をもたらそうとした。しかし、これらの事件を経ても、日本の政治体制は根本的に変わることはなかった。暴力による変革が劇薬となり得ることは否定しないが、近代化された日本においては、その力が無力であることは歴史的に証明されている。
それでは、他に方法はないのか。近代化された日本において、真の変革は暴力に頼ることなく、選挙という平和的手段を通じてこそ可能であると考える。政治体制を変革する力を持つのは、結局のところ有権者一人ひとりの一票であり、その一票を行使する私たちの意識と行動が、日本の未来を形作る鍵となる。
その意味でも、先に述べたように「勉強」が非常に重要だ。現代の世界情勢や日本の現状を知り、どのようにすればそれを克服できるのかを、一人ひとりが深く学び、理解することが必要である。選挙においても、単に一票を投じるのではなく、どの候補者が日本の未来にふさわしい選択肢を示しているのか、冷静に、かつ慎重に判断するための知識が求められる。勉強によって私たちは、真の変革をもたらす力を手にすることができるのだと、私は確信している。
健全な政治体制
昨年の衆院選で、国民民主党が一定の勢力を伸ばし、「103万円の壁」を撤廃しようという動きが現実味を帯びてきた。国民民主党がキャスティングボートを握ることで、官僚組織と戦う力を得たと言える。
しかし、私は決して国民民主党を盲目的に支持すべきだとは考えていない。日本が抱える経済的課題に対処するためには、民間の負担を軽減し、景気を刺激する政策を実行できる野党が必要だと私は思う。さらに、国体を破壊することなく、少数与党という政治状況を作り出すことが、今後の日本にとって重要なカギとなると考えている。
この考えは、明治天皇が五ヶ条の御誓文の中で掲げた「広く会議を興し、万機公論に決すべし」という言葉に通じている。つまり、多くの人材を集めて会議を開き、大切なことはすべて公正な意見で決めよう、という姿勢だ。この理念を実現するためには、真に機能する野党が必要であり、少数与党を含むバランスの取れた政治状況が不可欠だと私は信じている。
現実的には、現在の野党の多くは政権運営能力が未熟であるという事実がある。特に「悪夢の民主党時代」の経験があるため、野党に対して強い不安を抱く人々が多い。しかし、どの野党であれ過半数を超えなければ、政治的危機が現実となることはないだろう。もし危機が訪れるとしても、それと同等かそれ以上に深刻な経済的問題がすでに存在しているため、そちらを優先して考えるべきだと私は考える。
政治はゼロか百かの二択ではない。時々のバランスが重要であり、家計が消費を控え、企業が成長への投資をためらっている今、民間の負担を減らし、景気を回復させるためには、実際に力を持って働ける野党が不可欠だ。現実的な政治において、そうした勢力の存在が日本の未来を形作るうえで必要だと私は信じている。
政治家への道
時々、「それなら政治家になればいいのでは?」と言われることがある。しかし、私は自分のような考えを持っている者が政治家になることはないだろうと思っている。
選挙では、一貫した信念を持って行動する人に票が集まる。しかし、私の信念は「真に機能する野党と少数与党を含むバランスの取れた政治状況が良い日本を作る」というものだ。これは、いち政治家としての発想ではない。いち政治家としては、自らや自らの所属する党の勝利を目指して戦い、その執念が票に繋がるものだと思う。
もちろん、こうした考えを聞いて「そんなお前に政治を語る資格はない」と言う人もいるだろう。そんな人に、私はこう言いたい。「あなたのような考えを持つ人がいるから、今の日本があるのだ」と。
政治家でなければ社会を語る資格がない、という考えは、非常に危険な思想だ。社会について語ることは、政治家だけの仕事ではない。私たち一人ひとりが、声を上げ、考えを共有しながらより良い社会を作っていくべきだと思う。
なお、時折、私の言葉を聞いて「保守的だね」あるいは「革新的だね」と評されることがある。確かに、私は日本の歴史や伝統を深く愛しており、そのため保守的な立場を自認している。しかし、保守と革新の違いには実際、紙一重のものがあるのではないかという疑問を抱くことがある。
ある時、極左暴力集団の主張に触れたが、その中には私が共感する点が多々あったことを正直に認めざるを得ない。このことは、単なる立場の違いに過ぎないことを意味している。
日本の社会には、歴史的にも現代においても、世界に誇るべき素晴らしい面と、改善すべき問題が混在している。保守か革新かというラベルを掲げてのポジショントークには、私はあまり意味を見出さない。むしろ、重要なのは何が素晴らしいのか、何が問題なのかを見極め、それをどう発展させ、克服していくかという思考であると考える。
保守や革新の枠に囚われることなく、社会の抱える問題に真正面から向き合い、それを解決する道筋を見出すことが、真に社会を前進させるための鍵となるのではないだろうか。
目指したい未来
私たちが築く社会は、未来の子供たちのためにあると言っても過言ではない。現在、この社会で活躍している大人たちは、やがては老い、そして死を迎える。しかし、子供たちはその先に続く存在であり、今を起点にすると私たちよりも遥かに長い時間を生きる。彼らは未来を作り、次の世代を育てる役割を担っている。
そのことを踏まえると、私たちが今成すべきことは、彼らが希望を抱き、しっかりと生きていける社会を作ることである。この考えは理念的であるが、むしろ具体的な指標、すなわち「希望を持つ若者の数」という形で測定可能な目標でもある。
私は時折、夜の街で見知らぬ若者と会話を交わすことがある。そのたびに印象に残るのは、彼らが共通して金銭的な困窮を抱えているという事実だ。確かに、若者はいつの時代も金銭に困っている。しかし、現代の若者は、単に今お金がないというだけでなく、将来に対する深刻な不安を抱えているように感じる。それは、彼らが「今」抱える経済的困難が、将来の自分にとっても解消される見込みがないという、根本的な恐れを伴っているからだ。
そのような若者たちと何度か会い、飲み代やタクシー代を出すこともあったが、それがどれほどの意味を持つのか、今振り返ってみても明確には答えが出ない。しかし、それでも心は痛む。彼らが抱えるのは、金銭的な問題のみならず、未来への希望を見失っているという、もっと根本的な問題だと痛感する。
これから私が取り組みたいことは数多くあるが、その中心となるのは、「希望を持てる社会」を作ることである。たとえ社会に多くの困難があろうとも、希望を持つ若者がいれば、必ず良い方向へ進んでいくと信じているからだ。希望とは、ただの感情にとどまらず、変革を導く原動力である。希望を持てる環境を提供することこそ、私たちが果たすべき最も重要なことである。


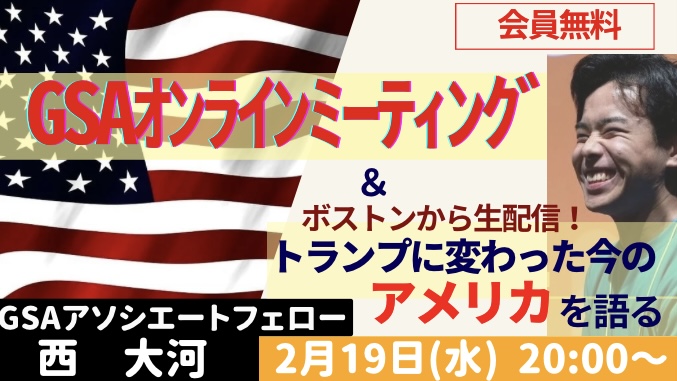
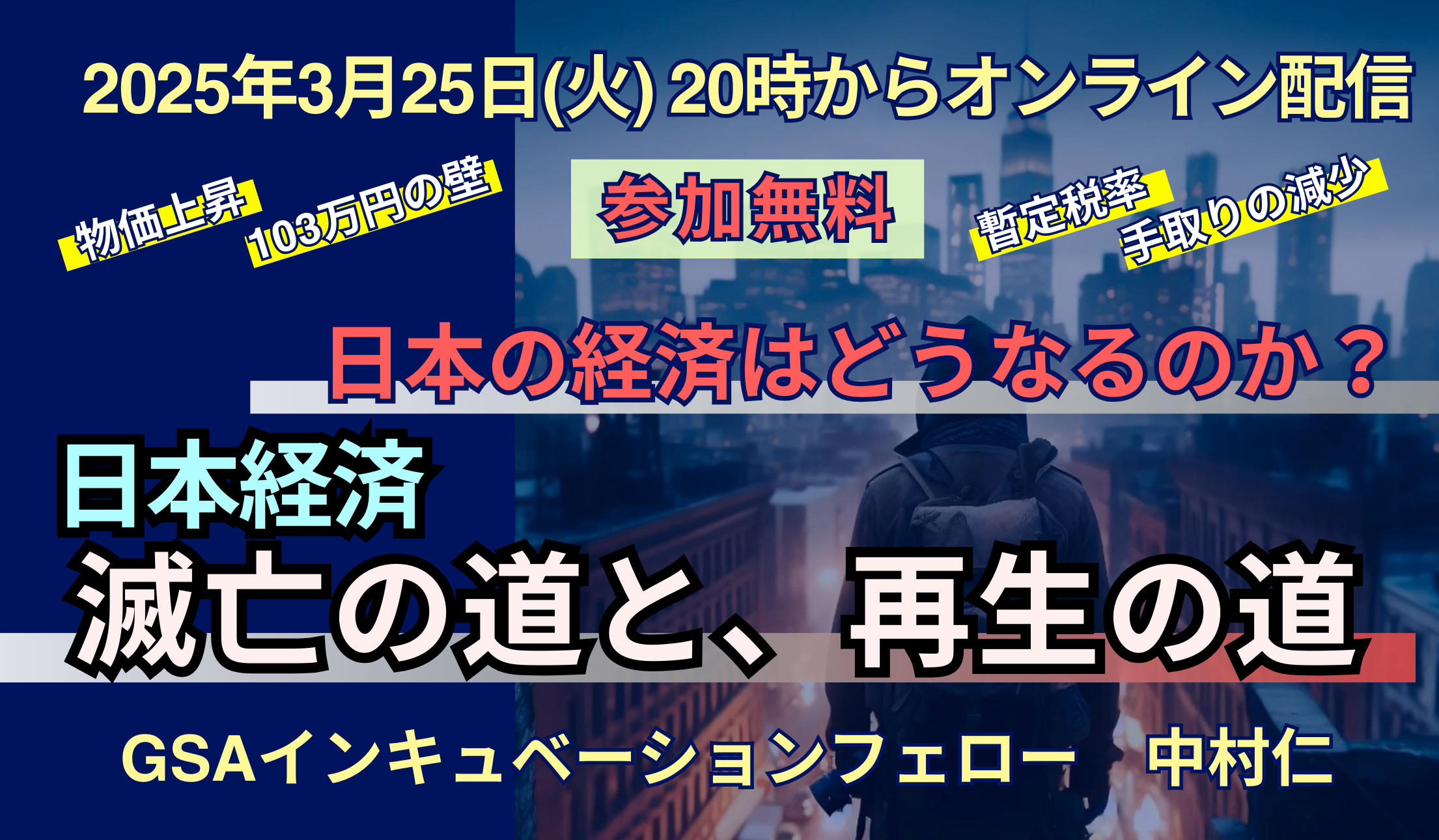
コメント